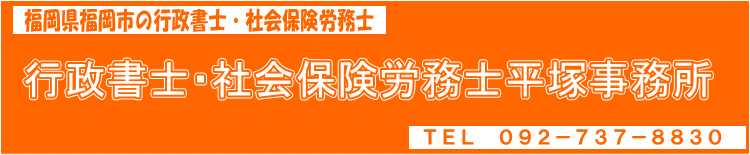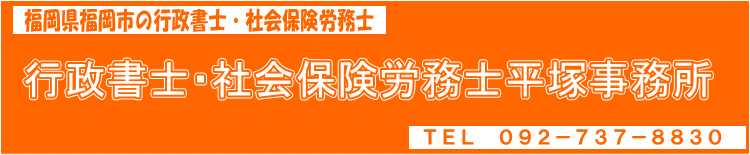<合同会社の設立>
<合同会社の特徴>
○法人格がある
合同会社は会社なので、法人格があります。株式会社と同じように会社名義での不動産の取得や賃貸契約をすることができます。
○株式会社への移行が可能
先ずは合同会社で設立登記をしておいて、会社の状況(事業の拡大、従業員を増やす)に応じて株式会社への移行も可能です。
○出資者が有限責任
社員(出資者)はすべて有限責任です。
会社が倒産した場合、会社の債務を個人財産で返済する義務はなく、自分の出資金が返ってこないだけで済みます。
*合同会社の社員の出資は、金銭その他の財産に限られ、設立の登記をするまでにすべての出資金額を払い込み、または、履行する必要があります
○社員1人の合同会社も認められます。
○他の法人も合同会社の社員になれます。
*法人が業務執行を行う場合は、「職務執行者」を選任しなければなりません。
○社員は全員が業務執行権を持つのが原則です。
定款により業務執行社員を選任すれば、その業務執行社員のみが業務執行権と代表権を持つことになります 。
<合同会社設立の簡単な流れ>
1.定款の作成
*公証役場で認証を受ける必要はありません
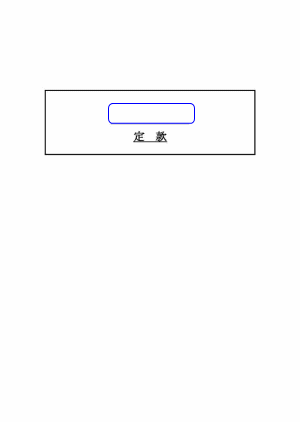
2.出資の払い込み(株式会社と同様に現物出資が可能)
*金額の払い込み、現物出資の給付が必要になります
3.設立登記申請(本店を管轄する法務局)
*登録免許税は6万円
4.設立登記の完了(福岡の場合は申請日から3週間程度です)
*合同会社の成立です。
会社成立後は、履歴事項全部証明書の取得や印鑑カードの申請(印鑑証明書)が可能となります。 また、法人成立後、銀行口座の開設や税務署や市役所、労働基準監督者などへの届出が必要となります。
合同会社の設立について
<合同会社のメリット>
○株式会社と比較すると会社設立費用(設立手続き上必要な支払い)が安い
◆株式会社の場合◆
・定款認証手数料:50000円
・定款謄本取得手数料:約1200円
・登録免許税:150000円
合計:201200円
◆合同会社の場合◆
・定款認証手数料:なし
・定款謄本取得手数料:なし
・登録免許税:60000円
合計:60000円
法定費用だけで14万円以上安くなります。
○個人1人、法人1社でも設立できる
合同会社の場合は、個人が1人で設立することも可能ですし、法人1社で設立して、出資と業務執行の両方の役割を果たすこといういうことも可能になります。(株式会社の場合は、法人1社で設立することはできません)
法人が業務執行を行う場合は、「職務執行者」を選任しなければなりません。
○配当金の分配比率を自由に設定することが可能
株式会社の場合、利益を分配する場合、株式をどれだけ保有しているか(どれだけ資本金を出しているか)で配当金の分配比率が決定されます。
※合同会社の場合、あらかじめ定款に定めておけば、資本金の出資比率とは異なる分配比率で配当金を出すことが可能となります。
つまり、資本金の出資した額が異なっていたとしても、配当金を平等に出すこと可能になります。
○役員の任期を定める必要がない
株式会社の場合は原則として取締役は2年・監査役は4年
(株式譲渡制限がある場合は、取締役・監査役ともに10年まで任期が延ばせます)と役員に任期が定められていますが、合同会社の場合は、定款で役員に任期を定めていない限り、任期は存在しないことになります
○社会保険に加入できる
合同会社は会社形態ですので、たとえ社員が1人の場合であっても社会保険に加入することができます。
○出資者が有限責任
有限責任とは、会社などへ出資した者がその出資した額についてのみ責任を負うということです。
つまり、社員として会社に出資して、その後会社が負債を抱え倒産した場合、社員は会社の債務について責任を負わない(支払う義務がない)ということです
会社に出資したお金は失うことになりますが、それ以上の損失を迫られることはない、個人財産で返済する義務はないということです。
*この有限責任というのは、出資した分の責任を負えばよいという意味での有限責任ですので、個人的に請け負った保証人としての負債などは返す義務がありますので、注意が必要です。
<合同会社のデメリット>
○株式会社と比べると認知度(信頼度)が低い
最近はだいぶ浸透はしてきましたが、合同会社という組織形態が世間一般に認知されるまでにはもう少し時間がかかりそうです。認知度が低いというのは、合同会社の最大のデメリットといえるでしょう。
確かに現時点では合同会社という会社組織の認知度(信頼度)は低いかもしれませんが、合同会社の数も増えてきています。
また、合同会社は株式会社への組織変更も可能です。事業規模が大きくなり、株式会社のほうがビジネス上都合がよいということになれば、株式会社への変更をご検討されることをお勧めします。
<合同会社の社員>
○社員全員の間接有限責任
合同会社の社員は、全員が有限責任であり、出資の価額を限度として合同会社の債務を弁済する責任を負いますが、合同会社の社員は、社員の資格を得る前に、必ず出資の全額の履行を終了しており、合同会社の債務を弁済する責任はありません。
○社員の持分の譲渡
会社成立後、社員の持分の全部又は一部を譲渡するには、定款に別段の定めをおく場合を除いて、原則として他の社員全員の承認が必要です。
ただし、業務を執行しない社員は、業務を執行する社員の全員の承認があるときは、その持分又は一部を他人に譲渡することができます。
◆持分を譲渡した社員の責任◆
持分の全部を譲渡した合同会社の社員は、譲渡後において、合同会社の債務の責任を行うことはありません。
○社員の加入
合同会社は、新たに社員を加入させることができます。
社員の氏名等は定款の記載事項であるため社員として認められるのは加入に関する定款の変更がされたときです。
*持分の譲受による場合は、譲渡人がすでに出資の全部を履行しており、新たな出資の履行の必要がないため、持分の譲受に関する定款の変更をしたときに譲受人は、合同会社の社員となります。
○社員の退社
合同会社の社員の退社には任意退社と法定退社があります。
◆任意退社◆
任意退社については、定款で任意に定めをすることができます。その内容は公序良俗に反しない限り、特に制約がありません。
特に制約がありませんが、会社法では退社の自由について一定のルールを定めています。
(定款で合同会社の存続期間を定めなかった場合またはある社員が生存している間合同会社が存続することを定款で定めた場合)
※6ヶ月前までに退社の予告をすることにより、各社員は、事業年の終了のときにおいて退社をすることができます。
◆法定退社◆
社員は以下の事由の発生により退社することになります。
①定款で定めた事由の発生
②総社員の同意
③死亡
④合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る)
⑤破産手続の開始の決定
⑥解散(④、⑤に掲げる事由によるものを除く)
⑦後見開始の審判を受けたこと
⑧除名
◆退社した社員の責任◆
合同会社を退社した社員は、退社する前と同様、合同会社の債権者に直接責任を負うことはありません。
<合同会社の業務執行者>
○業務執行社員
合同会社は定款の定め又は社員全員の同意により、社員の一部を合同会社の業務を執行する社員(業務執行社員)として定めることができます。
法人の社員も業務執行社員になることができます。
※業務執行社員を定款で定めた場合において、業務執行社員が2人以上いるときは、合同会社の業務は、業務執行社員の過半数によって決定します。
○業務執行社員の責任
1.善管注意義務
業務執行社員は、株式会社の取締役と同様に、善良な管理者の注意を持って、その職務を行う義務を負い、法令および定款を遵守し、合同会社のため忠実にその職務を行わなければなりません。
2.競業の禁止
業務執行社員は、他の社員の全員の承認を受けなければ、以下に掲げる行為を行うことはできません。
(1)事故又は第三者のために合同会社の事業の部類に属する取引をすること。
(2)合同会社の事業と同様の事業を目的とする会社の取締役、執行役または業務を執行する社員となること。
3.利益相反取引の制限
業務執行社員は、次に掲げる場合には、その取引についてその他の社員の過半数の承認を受けなければなりません。
(1)業務執行社員が自己または第三者のために合同会社と取引をしようとするとき
(2)合同会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でないものとの間において合同会社とその社員との利益が相反する取引をしようとするとき
4.業務執行社員の合同会社に対する損害賠償責任
業務執行社員は、任務懈怠があったときは、合同会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。
○業務執行社員が法人である場合
合同会社では、法人が業務執行社員になることもできます。
法人である場合、個人を職務執行者として選任して、その職務執行者については、その氏名及び住所を他の社員に通知しなければなりません。
その職務執行者についても、業務執行者と同一の善管注意義務・忠実義務・競業避止義務・利益相反取引の承認等の規制が課されています。
職務執行者の資格には制限はなく、社員たる法人の役員や従業員でない者、たとえば、顧問弁護士・会計士等を職務執行者とすることもできます。
<合同会社の代表者>
合同会社は、社員全員が合同会社の代表権を有しますが、社員の中から業務執行社員を定款で定めた場合は、業務執行社員が合同会社を代表します。
※業務執行社員が2名以上いる場合は、業務執行社員は、各自が合同会社を代表します。
また、定款または定款の定めに基づく社員の互選により、業務執行社員の中から合同会社を代表する社員(「代表社員」)を定めることができます。
業務執行社員が2名以上いる場合でその全員が代表権を持つとなると、ビジネス上で取引先が混乱する場合も考えられます。そのようなケースを防ぐ意味でも、株式会社のように代表を1人に決めてくおくことをお勧めします。
株式会社のような法人を代表社員として決めることもできます。
※その場合は、その法人の中から「職務執行者」1名を決める必要があります。多くの場合、職務執行者はその会社の取締役から選任します。
◆合同会社の代表者の第三者に対する責任◆
業務執行社員が第三者に対して、悪意または重過失により損害を与えた場合は、その業務執行社員が直接、第三者に対して連帯して損害を賠償しなければなりませんが、これに加えて、会社を代表する社員やその他代表者が、その職務を行うについて第三者に対して損害を加えた場合には、合同会社は、その損害を賠償する責任を負います。
<設立時の決定事項>
○商号
商号とは会社の名称のことです。どんな商号とを用いるかは基本的に自由ですが、すでにある会社と同じ商号を使用する際は注意が必要ですし、法律で使用が制限されている名称もあるので、事前によく確認しなくてはなりません。
○本店はどこにおくのか
本店とは、会社の本拠地のことです。
一般的には、主に業務を行っているところや、工場、店舗、事務所などの所在地を本店にします。自宅で開業する場合、自宅でもかまいません。ただし、架空の住所を本店の所在地にしてはなりません。
○会社の目的(事業内容)
会社の目的とは、会社が行う事業内容のことです。定款に定め、登記することで会社がどのような事業をしているのか公開されます。
会社の事業目的は、設立の際に決めたものに変更や追加があった場合、手数料を支払った上で手続を再度行わなければなりません。従って、設立の段階でできる限りすべての事業目的を盛り込むようにしましょう。
設立時に盛り込むべき事業は、
①
現時点で行っている事業、
②
今後行う予定のある事業
に関するものです。
*事業目的を決める際に大切なことは、許認可が関係する事業を行うかどうかです。事業によっては、許認可などの制度採用しているので、許可を取らなければ始められないビジネスもあります。
事業目的を決める際には、各種の営業許可・認可なども事前に十分注意する必要があります。
○資本金の額
以前は、株式会社は資本金を最低でも、1000万円にする必要がありましたが、現在ではいくらでもよくなりました。
1円でも、会社を設立させることができます。
しかし、その資金から会社の機材を購入したり、会社の必要経費を支払ったりしていくわけですから、現実的にはある程度の金額にしておくべきです。
◆資本金の額を決定するポイント
1.対外的信用から資本金額を決める
資本金の額は登記簿の記載事項となっています。資本金が多ければ多いほど、会社の対外的な信用は非常に高くなります。
*個人の専門技術や信用でビジネスをされる場合は、資本金の額はさほど問題にはされないでしょう。
2.運転資金から資本金額を決める
必要な運転資金から逆算して資本金の額を決定する方法があります。
1か月分の運転資金を割り出し、その6倍(半年)程度の運転資金を資本金として用意します。事業をスタートしてすぐに資金が底をつくというような状況は避けるべきです。ある程度の資本がないと、ビジネスはうまくいくことはありません。資本をしっかりと準備した上で事業をスタートされることをお勧めします
*また、同じ業種(同規模の会社)の資本金がいくらであるかを調べ、その金額をもとに資本金額を決定するのも1つの方法です。
○事業年度を決める
会社は1年ごとに会計の区切りをつけます。決算は、1年間に数回行うことも可能ですが、多くの会社が年1回の決算しています。
一般的に多いのが、「毎年4月から翌年3月31日」です。
決算期を決める方法としては、ビジネスの一番忙しい時期をはずしたり、税務を依頼している税理士にどの時期が都合がよいか希望を聞いて決算期を決定する方法があります。
<合同会社設立の流れ>
1.お電話又はフォームでのお申込み
2.基本事項を決定する 会社設立時の決定事項はこちら
◆会社の名前 ◆事業目的 ◆本店所在地 ◆社員の構成
◆事業年度 ◆資本金の額 ◆必要書類の説明
3.定款作成
4.資本金の証明をつくる 【振込証明書】
5.登記申請をする
◆必要書類◆
①1人でつくるLLCの場合
◆定款 ◆資本金決定書 ◆代表社員の印鑑証明書 ◆払込証明書 ◆資本金の額の計上に関する証明書
②2名でつくるLLCの場合
◆①の書類 ◆代表社員及び資本金決定書 ◆代表社員の就任承諾書
③3名でつくるLLCの場合
◆②と同じ書類
④法人が社員として入るLLCの場合
◆②の書類 ◆法人の登記事項証明書 ◆職務執行者の選任に関する書面◆職務執行者の就任承諾書
6.登記完了
役所の届出で必要になりますので登記簿謄本や印鑑証明書を取得しておきましょう。
7.各種届出
<設立後の届出>
*事前に各役所に提出書類・添付書類を確認しておきましょう
(税務署)
◆法人設立届出書
◆青色申告の承認申請書
◆原価償却資産の償却方法の届出書
◆棚卸資産の評価方法の届出書
◆給与支払い事務所等の開設届出書
◆源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
(都道府県税事務所)(市町村役場)
◆法人設立届出書
(年金事務所)
◆新規適用届
◆新規適用事業所現況書
◆被保険者資格所得届
◆被扶養(異動)届
(労働基準監督署)
◆保険関係成立届
◆概算保険料申告書
(公共職業安定所)ハローワーク
◆適用事業所設置届
◆資格取得届
◆保険関係成立届
<人を雇用をした時の手続き>
会社設立後、従業員を雇用したときの手続きです。
①労働契約
従業員を採用した場合、まず初めに労働契約を結びます。労働条件(契約期間・業務内容・所定労働時間を超える労働の有無など)を明示した労働契約書を交わすのが一般的です。
②社会保険の加入【健康保険・厚生年金】
社会保険の被保険者となる従業員を雇った場合、会社住所を所轄する年金事務所に届出をしなければなりません。
③労働保険の加入【雇用・労災】
【雇用】
雇用保険の被保険者となる従業員を雇った場合、翌月の10日までに、所轄のハローワークへ届出をしなければなりません。
【労災】
労災保険は、労働時間や契約期間の長短に関わらず、すべての従業員に適用されます。
<社会保険の切り替えについて>
従業員を雇用したときの手続きです。従業員を雇用するには主に次の3つのパターンがあると思います。
①学校(高校あるいは大学・専門学校)を卒業予定者(現在:国民健康保険に加入)を雇う。
②現在無職の方(現在:国民健康保険に加入)を雇う。
③転職の方を雇う。
上記①②の場合(国民健康保険➡新たな社会保険)の手続き
(会社側でやること)
●社会保険の加入手続き
国民健康保険から新たに社会保険に加入する手続きとなります。
(雇用された者がやること)
●健康保険被扶養者(異動)届の提出(会社に対して)
*通常、会社が書類を準備します。
●マイナンバーの通知(会社に対して)
*社会保険手続きで必要になります。
●国民健康保険の脱退手続き(住民票のある各市町村役場で)
*国民年金の脱退手続は必要ありません
(手続きの際持参するもの)
◆加入した社会保険の保険証(被扶養者分も)
◆国民健康保険の保険証(切り替える方全員分必要)
◆運転免許証など本人確認できるもの
上記③の場合(転職)の手続き
転職する場合、退職することになった会社では社会保険の資格喪失手続きを行う必要があります。
(退職する会社に提出するもの)
●健康保険被保険者証(被扶養者分も含めて)
転職をする場合の社会保険の手続きについては、次のAとBのパターンがあるかと思います。
A:退職してすぐに(退職翌日あるいは退職から2週間以内)に転職先の会社に入社
B:退職⇒無職の期間(2週間以上)⇒転職先の会社に入社
●Aの場合⇒新しい会社の方で社会保険手続を行うのみ。
●Bの場合⇒無職の期間がある場合、次のような選択肢があります。
(無職の期間が長い場合)
◆家族の扶養に入る
家族のうち、どなたか(配偶者など)、会社勤務をされている場合、その社会保険に被扶養者としてはいることが可能です
◆任意継続被保険者になる
会社を退職しても、社会保険(健康保険)をそのまま任意継続できる制度です。手続きは自分自身で、退職後20日以内に行う必要があります。
◆国民健康保険に入る
市町村での加入手続きが必要です。
*扶養家族がある場合、国民健康保険では被扶養者という仕組みがありませんのでその分保険料がかかってきます。
※社会保険の切り替え手続きについては、個別のパターンにより必要な書類が異なりますので事前に確認しておくことをお勧めします。
<役員報酬の決め方>
【損金処理(経費)できる役員報酬】
会社設立後、代表社員(業務執行者)の役員報酬をどのような方法で決定すればよいか、報酬額の決め方について説明致します。
役員に対して支払われる役員報酬を損金処理(経費扱い)するためには主に2つの方法があります。
①定期同額給与
②事前確定届出給与
①定期同額給与とは、「定期に、同額、支払われる役員報酬」のことです。
定期とは1ヵ月以内の一定期間のことであり、その期間であればどんな設定しても大丈夫です。
※「定期のスタート」「同額のスタート」は、決算終了後3か月以内であることが必要です。
②事前確定届出給与の要件は以下の2つ全て満たすことです。
(1)税務署に対して、役員ごとに「支給日」と「支給額」を事前に届け出る
(2)(1)の内容通りに正確に支給する
※「事前確定届出給与」の要件を満たせば、月次報酬とは別に、役員に対する年数回の報酬を損金として計上することが可能になります。
※「定期同額給与」は月次報酬で、「事前確定届出給与」は役員への賞与として考えることができます。また、「事前確定届出給与」を利用することで、非常勤役員に対し年1回の報酬も支払うこともできます。
「事前確定届出給与」の届出期限は、原則として以下のうちいずれか早い日となります。
・株主総会(社員総会)の決議日から1ヵ月を経過する日
・会計期間開始の日から4か月を経過する日
【役員報酬額の決め方】
役員報酬の決め方は主に次の2つがあります。
①予想される利益から決定
②希望する金額で決定
①予想される利益から決定
役員報酬を除いた会社の利益計画を作成し、残った利益の中から役員の報酬額を決定する方法。
利益計画で計算された金額の正確性が重要になります。
②希望する金額で決定
自分が希望する役員報酬額を決定し、その金額を受け取るために売上の向上や固定費の削減などを実行していくことになります。
売上向上のため、固定費の削減のため、利益計画を見直し、改善する必要があります
<会社にかかる税金>
①法人税(国税)
法人税とは、会社の所得に対してかけられる国の税金のことです。
法人税額 = 課税所得金額 × 法人税の税率
課税所得金額 = 益金 - 損金の額
(法人税の申告)
各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告しなければなりません。
法人税の納付)
申告書の提出期限である各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に納付しなければなりません。
②法人住民税(地方税)
法人に対して課税される住民税を法人住民税といいます。法人住民税は、以下の大きく2つに分類されます。
◆均等割:所得の有無に関係なく必ず課税。
◆法人税割:法人税額の一定割合が課税
法人住民税額=均等割額+法人税割
均等割額:会社の資本金の額と従業員数に応じて定められている、法人の規模に対する課税のことをいいます。
法人税割額:原則として国に納付する法人税額を基礎として課税されます。
(法人住民税の申告)
各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告しなければなりません。
(法人住民税の納付)
申告書の提出期限である各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に納付しなければなりません。
③法人事業税(地方税)
事業税は、企業の国内における事業活動に対して、都道府県が課している租税です。
法人事業税=課税所得金額 × 法人事業税の税率
(法人事業税の申告)
各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告しなければなりません。
(法人事業税の納付)
申告書の提出期限である各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に納付しなければなりません
④消費税(国税・地方税)
消費税は会社の取引に必ずついてまわる税金です。
消費税の納税義務の判定は、基準期間(事業年度)における消費税の課税売上高によって行われます。この基準期間の課税売上高が1000万円未満であれば消費税は免税となります。
基準期間とは、その課税期間の前々年度のことです。
<労働保険・社会保険>
労働保険
労災保険と雇用保険を総称して「労働保険」といいます。
労災保険は、業務を原因とする傷病になったときや職場への通勤途中で怪我をしてしまった場合に治療費等を受給するためのものです。
雇用保険は、退職した際に失業手当を受給したり、育児休業を取得した際に一定の給付金を受給したり、一定期間、国が指定する教育を受けた際に教育訓練給付を受給するために加入します。
社会保険
健康保険と厚生年金保険、介護保険を総称して「労働保険」といいます。
健康保険は、業務外で病気やけがをした時に医療機関で治療を受ける際に一定の自己負担額(3割)を負担することにより、残りの7割の金額が保険でカバーされる制度です。また、他にも「出産手当金」「傷病手当金」なども受給することができます。
厚生年金保険は、従業員が退職後、原則として65歳以降に年金を受給するためのものです。また、一定条件を満たすことにより、「障害厚生年金」や「遺族厚生年金」も受給できます。
介護保険は、40歳以上の従業員が一定の介護を受けなければならない状態になったときに介護を受けたり、保険医療サービスを受けるために加入するものです。
社会保険料料率は毎年度変更されます。
【月額分】標準報酬月額×保険料率
【賞与額】標準賞与額×保険料率
*保険料は事業主と従業員の折半負担
<当事務所に依頼するメリット>
1.会社設立前に会計税務に関する相談も受付けます。(税理士のご紹介)
*徳永喜樹税理士事務所 徳永氏のご紹介
2.会社設立後に事業資金の借入をご検討されている場合のご相談・事業計画書の作成もサポート致します。
*事業資金調達のサポートについて(当事務所のホームページ)
3.会社印鑑3点セットのサービス
【会社設立印鑑3点セットのプレゼント】
合同会社設立のお申込みのすべてのお客様にプレゼントさせていただきます


会社設立印鑑セット会社設立印鑑セット
①会社印
②代表社員の印(会社の実印)
③ 銀行印
4.会社設立後の労働保険・社会保険の保険成立の届け出を行います。
当事務所は社会保険労務士業務も行っています。
〇労働・社会保険の成立手続きについて ➡ 詳しくはこちらから
5.給与計算業務を大幅割引でお引き受けします。
*給与計算業務をご検討・ご希望の方のみ
大幅割引は、標準料金の半額を目安にお見積りいたします。
大幅割引の適用期間は「会社設立から1年間」となっております。
〇給与計算業務のホームページ(別のHPに移動) ➡ こちらからどうぞ
6.出勤・退勤管理、出勤簿管理、シフトの作成・管理をWeb上で行うシステムの導入サポートを大幅割引でお引き受けします。
*従業員の出勤・退勤管理、出勤簿管理・シフト管理をWeb上で行うシステム導入をご検討・ご希望の方のみ
大幅割引は、標準料金の半額を目安にお見積りいたします。
大幅割引の適用期間は「会社設立から1年間」となっております。
〇勤怠管理システムの導入サポートのホームページ(別のHPに移動)
➡ こちらからどうぞ
【会社設立後】
<労働保険・社会保険サービス及び3か月間の無料相談対応>
会社設立をご依頼いただいた方を対象とした特典です。
①労働保険・社会保険の届出書類作成、届出代行
○労働保険○
◆保険関係成立届
◆概算・増加概算・確定保険料申告書
◆雇用保険適用事業所設置届
*設立後1ヵ月以内に従業員を雇用された場合
◆雇用保険被保険者資格取得届
*設立後1ヵ月以内に従業員を雇用された場合
○社会保険○
◆健康保険 厚生年金保険 新規適用届
健康保険厚生年金保険 新規適用届
◆健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届
健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
②設立後3か月以内の無料相談対応
◆給与の決定方法
◆従業員の採用・雇用契約
◆労務管理について(労働時間管理など)
◆会社の内部規定・協定について(就業規則・36協定など)
<ご準備いただくもの>
○印鑑証明書と実印
・社員(出資する人)となられる方
○個人の銀行口座(資本金を振込)
○現物出資をお考えの方はその資料
(車ならば車検証、機械などはその型式などが特定できる書類)
*会社への出資は現金だけでなく、不動産や自動車などの財産も出資することができます。これを「現物出資」といいます。
<料金について>
○合同会社設立 総額 10万9200円 (税別)
※会社印鑑3点セットプレゼント
(内訳)
・事務所報酬 : 4万8千円
・法務局での費用<登録免許税> : 60000円
・登記事項証明書2通 : 1200円
【書類作成のみのサービス】(会社印鑑3点セットは含まれていません)
○書類作成のみ 総額 3万円 (税別)
(内訳)
・事務所報酬のみ : 3万円
*書類作成のみサービスの場合について
・会社印鑑はお客様ご自身でご準備いただきます。
・書類への印鑑押印方法などは事務所にて直接ご案内させていただきます。
・会社設立後の役所への届出についてもご案内いたします
お電話あるいは下記のメールフォームよりご連絡くださいませ。
◆電話:092(737)8830 事務所までの地図
◆お問い合わせ・お申し込み お問い合わせは無料です。
◆事務所での面談相談のお申し込み 30分:3千円
◆無料メール相談 回答の返信は48時間以内が目安です。
◆出張相談 福岡県限定 1時間:1万円
◆電話相談 30分:3千円 お問い合わせのお電話は無料です。
|